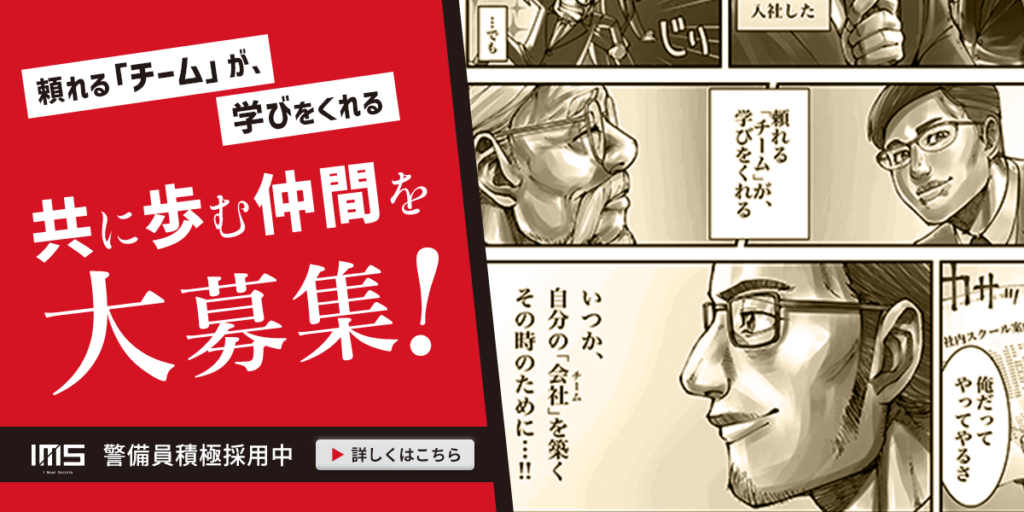Blog ブログ
警備員になるには?ゼロから始める手順と必要書類【資格なしでもOK!】
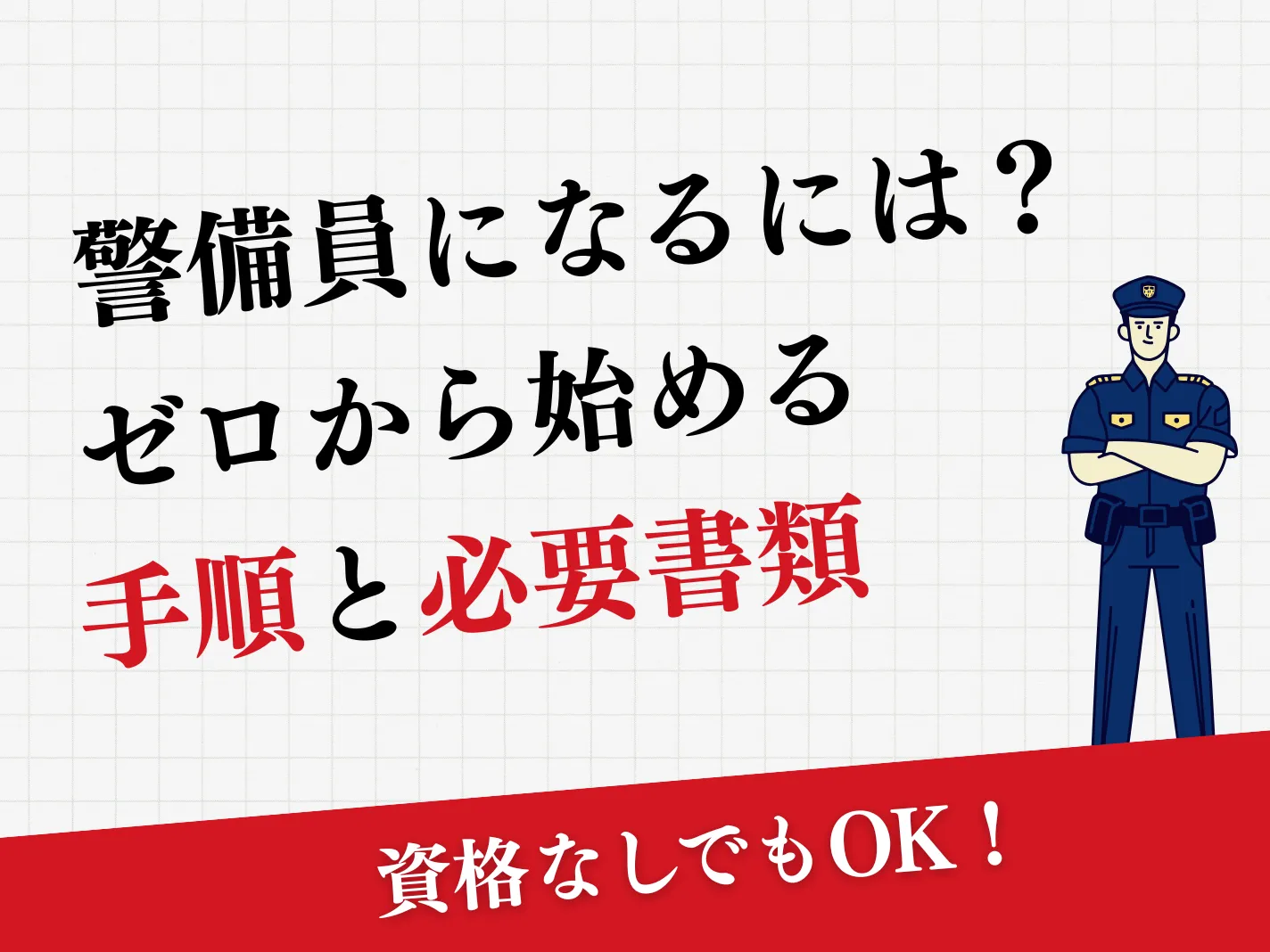
「警備員になってみたいけど、何から始めればいいのか分からない…」
そんな方のために、この記事では警備員になるための手順や必要書類をゼロからわかりやすく解説します。
警備員の仕事は、施設の安全を守る「1号警備」から、イベントでの誘導や交通整理を行う「2号警備」、さらには貴重品の輸送や身辺警護など、さまざまな分野に分かれています。
未経験からこれらの警備員になるのに特別な資格は必要なく、年齢制限もない警備会社が多いことから、転職やセカンドキャリアにも人気の職種です。
この記事では、警備員になるための流れを8つのステップに分けて解説し、用意すべき書類や採用試験に受かるためのコツなども分かりやすくまとめました。
これから警備員を目指すあなたの第一歩に、ぜひお役立てください!
警備員になるための8つのステップと必要書類

警備員の仕事に興味はあるけれど、「どうやってなるの?」「何を準備すればいいの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
警備員は特別な資格がなくてもスタートできる職種ですが、事前に確認すべき条件や必要書類、採用後の研修など、押さえておくべきポイントがいくつかあります。
ここでは、未経験の方でも安心して警備員を目指せるように、警備員になるためのステップを8つに分けてわかりやすく解説します。
応募から勤務開始までの流れをしっかり確認して、警備員への第一歩を踏み出しましょう。
「警備員になれない人」に該当していないか確認する
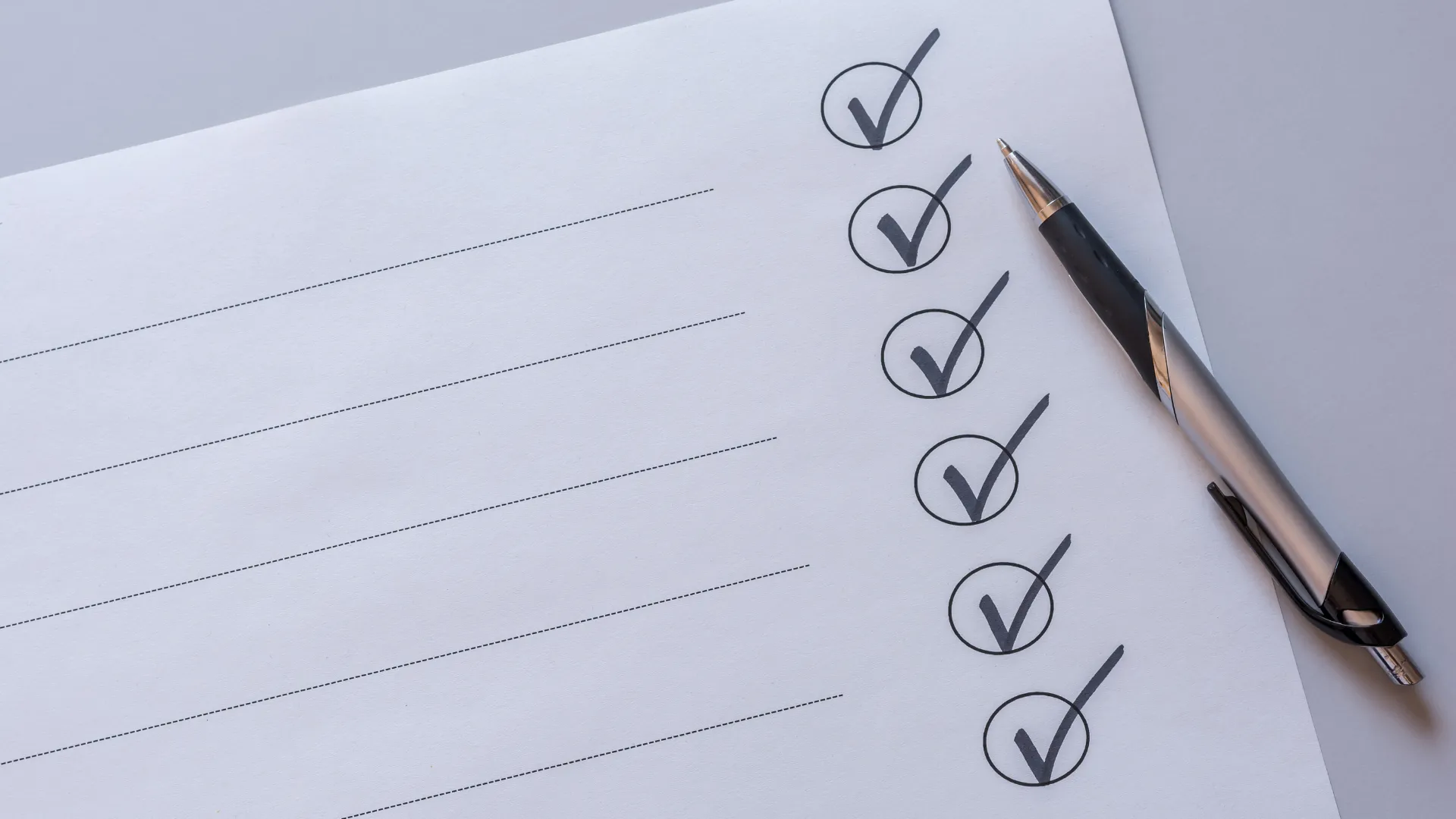
警備員として働くためには、警備業法に定められた8項目の欠格事由(法人や役員の場合は11項目)に該当しないことが必須です。
これは、警備業務が国民の生命、身体、財産を守るという重要な役割を担うため、その業務に適格な人物であるかを厳しく審査するためです。
具体的には、以下の項目に当てはまる場合は警備員になることができません。
- 十八歳未満の未成年者
- 破産手続き中か、破産決定後に免責を得られずに復権できなかった者。
- 刑務所に服役する刑罰(拘禁刑)を受け、刑務所を出所してから5年経過しない者。警備業法違反においては罰金刑でも該当し、罰金を納付してから5年経過しない者も同様の扱いです。
- 最近5年間に警備業法に違反した者(警備業に携わっていなければ該当しない)
- 集団的・常習的な罪を犯すおそれのある者
- 暴力団対策関連で処分を受けて3年経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの中毒者
- 精神機能の障害があり、警備業務を適正に行えないと診断される者
参考: 警視庁「https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/style/oath.files/2025_keibi.pdf 宣誓書(PDF)」(2025年7月11日参照)
これらの欠格事由は、警備業法第十四条に詳細が規定されています。
もし、ご自身がこれらのいずれかに該当する可能性がある場合は、事前に専門家や警備会社に相談することをおすすめします。
警備員の種類を知る

警備員と一言で言っても、その業務内容は多岐にわたります。
自身の適性や興味に合わせて、どの警備を目指すかを考えることが重要です。
警備業法第二条で定められている主な警備業務は以下の4つです。
- 1号警備業務(施設警備)
- 2号警備業務(交通誘導・雑踏警備)
- 3号警備業務(貴重品運搬警備)
- 4号警備業務(身辺警護)
それぞれの警備業務について、詳しく解説します。
1号警備業務(施設警備)
施設内の巡回、監視、出入管理、防犯カメラのチェック、緊急時の初期対応などを行います。
オフィスビル、商業施設、病院、学校、工場、金融機関、ホテル、イベント会場など、多種多様な場所で実施されます。
比較的体力的な負担が少なく、注意力や集中力、きめ細やかな対応が求められます。
また、やや特殊な例としては、店舗内での盗難防止を目的とした「保安警備業務(通称:万引きGメン)」も1号警備業務に含まれます。
2号警備業務(交通誘導・雑踏警備)
工事現場や駐車場、イベント会場などで、車両や歩行者の安全な通行を誘導します。
道路工事現場、建設現場、駐車場、お祭りやコンサートなどのイベント会場などで実施されます。
屋外での業務が多く、天候に左右されることがあります。
旗振りなどの動きはありますが、長距離の移動や重い物の運搬などはほとんどありません。
状況判断能力や、はっきりとした声出し、的確な指示出しが求められます。
3号警備業務(貴重品運搬警備)
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
銀行、企業、美術館などから、指定された目的地へ安全に運搬し、引き渡すまでの業務も含まれています。
専門性が高く、防犯意識や緊急時の対応能力が非常に重視されます。
求人数は他の警備業務に比べて少ない傾向があります。
4号警備業務(身辺警護)
要人や著名人、一般の方の生命、身体の安全を確保するため、付き添って警護します。
移動中や滞在先など、警護対象者に同行して警護します。
高度な専門スキル、判断力、状況分析能力が求められます。
身体能力だけでなく、心理的な洞察力も重要です。
こちらも求人数は少ない傾向にあります。
ご自身の興味や体力、適性に合わせて、どの警備業務に挑戦するかを検討してみてください。
警備員の求人情報を調べる

警備員の求人を探す方法は、主に以下の5つです。
- 求人情報サイト
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 警備会社の採用ホームページ
- 新聞折込チラシ・地域の情報誌
- 知人・友人からの紹介
それぞれの方法について、詳しく解説します。
求人情報サイト
Indeed、リクナビNEXT、マイナビ転職などの大手求人情報サイトでは、多数の警備員の求人が掲載されています。
「警備員」「施設警備」「交通誘導」「イベント警備」など、具体的なキーワードで検索することで、希望の業務内容や勤務地、給与条件に合った求人を見つけやすくなります。
また、これらのサイトでは、企業の特徴や口コミなども参考にできます。
2号警備の場合は、タウンワーク、バイトル、マッハバイトなどのアルバイト向けの媒体でも求人が多く出ているので、チェックしてみましょう。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークは、地域の求人情報を網羅している公的な機関です。
警備会社の求人も多く取り扱っており、専門の職員が相談に乗ってくれたり、職業訓練の案内なども行っています。
また、ハローワークでしか扱っていない求人もありますので、積極的に利用してみる価値はあります。
警備会社の採用ホームページ
大手警備会社や地域密着型の警備会社は、自社の採用ホームページで積極的に求人情報を公開しています。
会社の雰囲気や福利厚生なども詳しく記載されていることが多いため、気になる会社は個別に確認してみましょう。
特に大手警備会社は、全国各地で様々な種類の警備業務を行っているため、選択肢の幅が広いです。
関東・東北・中国地方を中心にサービスを展開する警備会社の弊社株式会社IMSも、ホームページの警備員の未経験者向け採用ページで求人情報を公開しているので、未経験から警備員になりたいという方は、ぜひチェックしてみてください。
新聞折込チラシ・地域の情報誌
地域の警備会社が、地元向けの求人として新聞折込チラシや地域の情報誌に掲載していることもあります。
特に未経験者歓迎の求人や、短期間のイベント警備の求人などが見つかることがあります。
知人・友人からの紹介
警備員として働いている知人や友人がいれば、その会社で募集している求人を紹介してもらうのも一つの方法です。
会社の雰囲気や仕事内容について、リアルな情報を聞くことができるメリットがあります。
必要な書類を用意する

警備会社への応募にあたり、いくつかの書類が必要となります。
これらの書類は、応募者の基本的な情報や適格性を判断するために用いられます。
事前に準備しておくことで、スムーズに応募手続きを進めることができます。
一般的に必要となる書類は以下の2つです。
- 履歴書
- 身元確認書類
また、会社によっては、以下の書類の提出も求められる場合があります。
- 職務経歴書(職歴がある場合)
それぞれに記載する内容などを詳しく解説します。
履歴書
学歴、職歴、資格、免許などを正確に記載します。
志望動機は具体的に、警備員として働くことへの熱意や、その会社で貢献したい意欲が伝わるように書くことが大切です。
誤字脱字がないよう、丁寧に作成しましょう。
身元確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど、顔写真付きで公的に本人確認、住所確認ができるものが必要です。
職務経歴書(※会社によっては提出が必要)
これまでの職務経験、担当業務、実績などを具体的に記述します。
警備員としての経験がない場合でも、これまでの仕事で培った責任感、コミュニケーション能力、協調性などが警備業務に活かせることをアピールすると良いでしょう。
特に、チームで協力して何かを成し遂げた経験や、顧客対応の経験などは高く評価されることが多いです。
応募する

必要な書類が全て揃ったら、いよいよ応募です。
応募方法は、求人情報によって異なりますが、主に以下のいずれかの方法が取られます。
- Web応募
- 郵送応募
- 電話応募
- 来社応募(オープンカンパニー、会社説明会など)
それぞれの応募方法の特徴を解説します。
Web応募
求人情報サイトや警備会社の採用ホームページから、オンラインで応募する方法です。
応募フォームに必要事項を入力し、履歴書や職務経歴書などのファイルを添付して送信します。
手軽に応募できる反面、誤入力がないように注意が必要です。
応募完了後に、入力内容の確認画面や自動返信メールが届くことが多いので、必ず確認しましょう。
弊社株式会社IMSでも、ホームページの警備員の未経験者向け採用ページからオンラインでの応募が可能となっています。
「まずは話を聞くだけ」でも勿論構いませんので、お気軽にご連絡ください!
郵送応募
履歴書や職務経歴書などの必要書類を封筒に入れ、会社宛に郵送する方法です。
送付状を同封し、A4サイズのクリアファイルに入れて郵送すると、より丁寧な印象を与えられます。
到着までに時間がかかるため、締切に余裕をもって送付しましょう。
書類に折り目や汚れがつかないよう、丁寧に梱包することも大切です。
電話応募
求人情報に記載されている連絡先に電話し、面接の日程調整を行う方法です。
電話口では、氏名、応募職種、連絡先などを簡潔に伝え、担当者の指示に従いましょう。
メモを取りながら対応し、聞き間違いがないように復唱確認すると良い印象を与えられます。
電話の際に、面接に必要な持ち物や、応募書類の持参の有無などを確認しておくとスムーズです。
来社応募(オープンカンパニー、会社説明会など)
企業によっては、事前に会社説明会やオープンカンパニーを開催し、その場で応募を受け付けているケースもあります。
会社説明会に参加することで、企業の雰囲気や仕事内容を直接知ることができるため、入社後のミスマッチを防げるというメリットがあります。
その場で応募書類を提出する場合もありますので、事前に必要書類を持参するように指示がないか確認しておきましょう。
採用試験を受ける

警備員の採用試験は、一般的に以下の選考ステップで実施されます。
- 書類選考
- 筆記試験(適性検査、一般常識など)
- 面接
それぞれの選考ステップについて、詳しく解説します。
書類選考
まずは、応募書類の内容を確認して、書類選考が行われます。
履歴書や職務経歴書は、あなたの第一印象を左右し、面接に進めるかどうかの重要な判断材料となります。
今までの経歴で、警備員の仕事の役に立つようなエピソードなどがあれば、存分にアピールしましょう。
応募する会社の情報をよく調査し、共感できる部分などを見つけ、PRするのも良いでしょう。
また、入社後のミスマッチを防ぐために、勤務条件に希望があれば、忘れずにしっかりと記載することも重要です。
筆記試験(適性検査、一般常識など)
警備員の採用試験は、書類選考→面接という選考ステップの場合も多いですが、警備会社によっては、筆記試験を実施する場合もあります。
筆記試験では、「適性検査」や「一般常識」を実施する警備会社が多いです。
「適性検査」は、性格や行動特性が警備業務に向いているかを測るものです。
特別な対策は不要ですが、正直に回答することが大切です。
「一般常識」は、社会情勢、時事問題、国語、算数など、基本的な学力や一般教養を確認するものです。
日頃からニュースに関心を持つなど、基本的な知識を身につけておきましょう。
また、書店などで売っている一般常識対策の参考書を購入して理解度を深めると良いでしょう。
面接
最も重要な選考ステップです。
警備員としての適性、コミュニケーション能力、責任感、協調性などが見られます。
服装はスーツやビジネスカジュアルなど、清潔感のある服装を心がけましょう。
指定がない場合は、スーツが無難です。
面接では、以下のような質問をされる場合が多いです。
- 志望動機、自己PR
- 警備員になりたい理由、なぜこの会社を選んだのか
- 警備業務への理解度、イメージ
- これまでの職歴、経験(警備未経験でも、これまでの経験から警備業務に活かせる点をアピール)
- 体力面での不安や健康状態
- 夜勤や不規則勤務への対応可否
- 長所、短所
- 入社後にやりたいこと、将来の目標
会社のウェブサイトやパンフレットなどで企業情報を事前に調べ、警備業務に関する基本的な知識を身につけておきましょう。
また、想定される質問に対する回答を事前に準備し、模擬面接などで練習することで、本番でスムーズに答えられます。
質問に対しては、簡潔かつ具体的に答えることを意識しましょう。
内定先の会社で新任教育を受ける

採用試験に合格し、内定が出たら、いよいよ警備員としての第一歩を踏み出すための「新任教育」が始まります。
警備業法施行規則37条に基づき、すべての警備員は警備業務に従事する前に、合計20時間以上の新任教育を受けることが義務付けられています。
この教育は、警備員として必要な知識、技能、心構えを習得するための非常に重要な期間です。
新任教育の内容は、警備業務の区分に関係なく共通した内容の「基本教育」と、それぞれ従事する業務の区分に合わせた内容の「業務別教育」があります。
新任教育は、座学と実技の両方で行われることが一般的です。
座学では法令や基本原則を学び、実技では護身術や資機材の操作、交通誘導の実践などを通じて、即戦力となるためのスキルを磨きます。
この期間は、警備員としての基礎を築く上で非常に重要です。
積極的に質問し、疑問点を解消しながら、一つ一つの内容をしっかりと理解し、習得するように努めましょう。
教育担当者や先輩警備員とのコミュニケーションを通じて、現場での実践的な知識や心構えを学ぶこともできます。
以下に、基本教育と業務別教育で学ぶ具体的な内容の例をまとめました。
基本教育の内容例
- 警備に必要な基本的動作(礼式・敬礼・姿勢など)
- 警備業法や関係法令の基礎知識
- 緊急時の初期対応と応急手当の基本 など
1号警備の業務別教育の内容例
- 巡回・立哨の基本と実施手順
- 出入管理の方法と来訪者対応
- 不審者・火災時などの緊急対応 など
2号警備の業務別教育の内容例
- 誘導灯や手信号の使用方法
- 車両・歩行者の安全な誘導手順
- 現場での危険予測と事故防止策 など
3号警備の業務別教育の内容例
- 貴重品輸送の基本的な流れ
- 車両・ルートの安全確認と管理
- 襲撃などへの緊急時対応方法 など
4号警備の業務別教育の内容例
- 護衛対象者の安全確保と動き方
- リスク予測と緊急回避行動の基本
- 不審者や危険人物への対応手順 など
警備員として働き始める

新任教育を無事に修了したら、いよいよ警備員として現場での勤務が始まります。
初めは不安に感じることもあるかもしれませんが、ほとんどの会社では、新任教育後もOJT(On-the-Job Training)と呼ばれる現場での実地指導や、先輩警備員によるサポート体制が整っています。
警備会社である弊社株式会社IMSでは、初めての警備業でも安心して現場での業務をこなせるよう、先輩警備員がしっかりサポートします。
また、警備業でキャリアアップしていきたい方のために、資格取得を全力で支援しています。
さらに、将来的に警備業で独立をしたいという方のために、業界トップクラスの独立支援制度を整えています。
警備業での独立のノウハウ、開業資金、先輩社長からのアドバイスなど、社長を目指す方をグループ全体で支援しています。
弊社に興味を持った方は、「まずは話を聞くだけ」でも勿論構いませんので、ホームページの警備員の未経験者向け採用ページからぜひお気軽にご連絡ください!
警備員として採用してもらうために必要な対策は?

警備員の面接では、警備員としての適性や人物像が重視されます。
具体的なスキルや経験ももちろん大切ですが、それ以上に「信頼できる人物か」「責任感を持って業務を遂行できるか」「冷静な判断ができるか」といった点が評価のポイントとなります。
ここでは、警備員になるために必要な準備をいくつかご紹介します。
清潔感のある身だしなみを心がける
警備員は、施設の「顔」となる存在であり、常に人々の目に触れる仕事です。
そのため、清潔感は非常に重要です。
- 服装:スーツが無難ですが、会社の指示があればそれに従いましょう。もし私服での面接が許可されていても、襟付きのシャツや落ち着いた色のジャケットなど、清潔感のある服装を選びましょう。
- 髪型:清潔に整え、顔にかからないようにしましょう。
- 髭・爪:きちんと手入れをしましょう。
- 靴:磨かれた綺麗な靴を履きましょう。
- 匂い:香水などの強い香りは避け、無臭を心がけましょう。
志望動機と自己PRを明確にする
「なぜ警備員になりたいのか」「なぜこの会社で働きたいのか」を具体的に伝えられるように準備しましょう。
「志望動機」は、「人々の安全を守りたい」「社会貢献したい」といった漠然としたものではなく、具体的なエピソードを交えたり、応募先の会社のどのような点に魅力を感じたのかを伝えることで、説得力が増します。
例えば、「過去にイベント警備を見て、そのプロ意識に感銘を受けた」「貴社の〇〇という理念に共感した」など、具体的に述べると良いでしょう。
「自己PR」は、これまでの経験で培ってきた強み(責任感、協調性、冷静な判断力、体力、コミュニケーション能力など)を、警備業務でどのように活かせるかを具体的にアピールしましょう。
警備未経験の場合でも、前職での経験から警備に通じる要素(例えば、接客業でのクレーム対応経験、チームでの協力経験など)を挙げると効果的です。
警備業務への理解度を示す
警備員の仕事内容について、ある程度の知識を持っていることをアピールしましょう。
警備業務には様々な種類(施設警備、交通誘導警備など)があることを理解し、それぞれの業務内容について把握していることを示しましょう。
また、警備業務には夜勤や立ち仕事、緊急時の対応など、体力面や精神面で大変な側面があることも理解していることを伝え、「それでもやりたい」という意欲を見せることが重要です。
体力面・健康面での問題がないことを伝える
警備業務は体力を使う仕事であり、健康状態が非常に重要です。
現在、持病がなく健康であることを明確に伝えましょう。
警備業務に必要な体力があることをアピールしましょう。
「ウォーキングを日課にしている」「以前スポーツをしていた」など、具体的に体力維持に努めていることを伝えられると良いでしょう。
冷静な判断力と対応能力をアピールする
緊急時やトラブル発生時に冷静に対応できる能力は、警備員にとって不可欠です。
過去にトラブルに遭遇した際に、どのように冷静に対応し、解決したかのエピソードがあれば具体的に伝えましょう。
ストレスを感じたときの対処法や、プレッシャーに強いことなどをアピールすることも有効です。
コミュニケーション能力を意識する
警備員は、来訪者や関係者、同僚とのコミュニケーションが頻繁に発生します。
面接官の質問をよく聞き、的確に答えることを心がけましょう。
明るく、ハキハキと、礼儀正しい言葉遣いを心がけましょう。
警備員に関するよくある質問

警備員の年収は?
警備員の年収は、警備業務の種類、勤務形態(正社員、アルバイト・パート)、勤務地(都市部か地方か)、会社の規模、経験、保有資格など、様々な要因によって大きく変動します。
一般的に、正社員の警備員の年収は、300万円~400万円台がボリュームゾーンと言われています。
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、警備員の平均年収は約350万円程度と報告されています。
これはあくまで平均値であり、実際には警備業務の種類、勤務形態、経験・資格、勤務地・会社規模などによって差が生じます。
また、警備員の給与体系は、月給制、日給月給制、日給制、時給制など、会社や業務内容によって様々です。
求人情報を確認する際には、基本給だけでなく、各種手当や賞与の有無、残業代の支給方法なども詳しく確認するようにしましょう。
年収アップを目指すのであれば、正社員として安定した会社で経験を積み、積極的に資格取得に励むことが重要です。
警備員の年収をアップさせるためのコツは、以下の記事で解説していますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
未経験でも警備員になれるの?
はい、未経験からでも警備員になることは十分に可能です。
警備業界は常に人財を求めており、特に未経験者歓迎の求人が多く存在します。
多くの警備会社は、法定研修に加え、会社独自の研修やOJT(On-the-Job Training)を充実させており、現場で実践的に業務を覚えられるようサポート体制を整えています。
また、警備業界は慢性的な人手不足にあり、未経験者であっても積極的に採用する傾向にあります。
そのため、比較的就職しやすいと言えるでしょう。
未経験だからといって諦める必要はありません。
むしろ、新しいことに挑戦する意欲や、素直に学ぶ姿勢は、警備会社から高く評価されるでしょう。
警備会社である弊社株式会社IMSでは、未経験の方でも安心して現場での業務をこなせるよう、先輩警備員がしっかりサポートしています。
弊社に興味を持った方は、ホームページの警備員の未経験者向け採用ページからぜひお気軽にご連絡ください!
体力に自信がないけど大丈夫?
「体力に自信がない」と感じている方でも、警備員として働くことは十分に可能です。
警備業務は多岐にわたり、体力的な負担が少ない職種も存在するため、一概に「体力がないと務まらない」と決めつける必要はありません。
例えば、比較的体力的な負担が少ない施設警備は、体力に自信がない方でも始めやすい職種です。
特に、座ってモニター監視を行う業務が多い「機械警備基地局での監視業務」や「常駐警備施設での防災センター要員」などは、身体への負担が少ない傾向にあります。
面接の際に、自身の体力について正直に伝え、どのような警備業務であれば無理なく働けるかを相談してみるのも良いでしょう。
会社によっては、個々の体力レベルに合わせた配属を考慮してくれる場合があります。
警備員には、体力だけでなく、冷静な判断力、責任感、注意力、コミュニケーション能力など、様々な能力が求められます。
体力に自信がない場合でも、これらの他の能力を活かすことで、警備員として十分に活躍できます。
まずは、自身の体力レベルに合った警備業務や勤務形態を探し、積極的に求人情報を確認してみましょう。
女性でも警備員になれるの?
はい、もちろん女性でも警備員になれます。
むしろ、近年では女性警備員の需要が高まっており、多くの警備会社が女性の採用に積極的です。
女性の目線で、来訪者への案内や困っている人へのサポートなど、きめ細やかな対応ができる点が評価されています。
商業施設や病院、学校など、女性の利用者や子どもが多い施設では、女性警備員がいることで安心感を与えることができます。
また、工事現場(2号警備)での警備においても、主婦目線や母親目線での近隣住民への配慮が高く評価されている事例もあります。
トラブル発生時でも、男性に比べて威圧感が少なく、落ち着いた対応ができるため、事態の悪化を防ぎ、円滑な解決に繋がりやすいとされています。
言葉遣いや立ち居振る舞いが丁寧であるため、企業のイメージアップにも貢献します。
もちろん、警備業務には体力が必要な場面もありますが、適切な装備や訓練、そして何よりも「安全を守る」という強い意識があれば、性別に関係なく活躍できます。
体力に不安がある場合は、施設警備など、比較的体力的な負担が少ない業務を選ぶことも可能です。
女性で警備員を目指す方は、まずは女性警備員を積極的に採用している警備会社を探してみたり、女性警備員が実際に働いている現場を見学してみるなど、情報収集から始めてみることをおすすめします。
自身の持つ強みを活かし、社会に貢献できるやりがいのある仕事です。
年齢が高いけど大丈夫?
はい、年齢が高い方でも警備員になることは十分に可能です。
警備業界では、幅広い年齢層の人が活躍しており、特に定年後のセカンドキャリアとして警備員を選ぶ方も少なくありません。
長年の社会経験で培われたコミュニケーション能力、対応力、判断力は、警備業務において非常に高く評価されます。
様々な状況に遭遇した経験が、冷静な判断や的確な対応に繋がることが多くあります。
若者にはない落ち着きや包容力は、施設利用者や通行人に対して安心感を与え、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
多くの警備会社では、年齢よりも人柄や真面目さ、責任感を重視して採用を行っています。
定年退職後も社会と関わりを持ちたい、やりがいのある仕事がしたいと考えている方にとって、警備員は非常に魅力的な職業です。
まずは、ご自身の体力や希望する勤務形態を考慮し、未経験者歓迎やシニア歓迎の求人を探して、積極的に応募してみることをおすすめします。
まとめ|警備員になるには、安心して働ける環境を選ぶことが重要
警備員の仕事は、特別な資格がなくても始めることができ、年齢や経歴を問わず幅広い方がチャレンジしやすい職種です。
施設警備や交通誘導、イベント警備など業務の幅も広く、自分に合ったスタイルで働ける点も大きな魅力といえるでしょう。
この記事では、警備員になるための基本的なステップとして、欠格事由の確認から求人の探し方、必要書類の準備、そして採用後の流れまでを、初めての方にもわかりやすく解説してきました。
警備員として安心して長く働き続けるためには、現場をしっかり支えてくれる環境を選ぶことが何よりも重要です。
警備会社である弊社株式会社IMSでは、未経験からスタートする方でも無理なく現場に馴染めるよう、経験豊富な先輩警備員が一つひとつ丁寧にサポートしています。
加えて、資格取得支援制度やキャリアアップに向けた研修制度も充実しており、「手に職をつけたい」「腰を据えて働きたい」と考える方にとって、非常に心強い環境が整っています。
さらに、将来的に独立を目指す方には、業界トップクラスの独立支援制度を用意しています。
開業資金の相談からノウハウの提供、先輩経営者によるアドバイスまで、グループ全体でのバックアップ体制が整っているのも大きな強みです。
また、弊社IMSでは紹介へのお礼として紹介料という制度があります。
1人で面接に行くのが心細い方、最初から友人・知人と共にご応募ください。
紹介料はどちらか誰かお一人への支払いとなりますが割り勘して頂いても構いません!
「少し興味がある」「まずは話を聞いてみたい」といった方も、もちろん大歓迎です!
弊社に興味をお持ちの方は、ホームページの警備員の未経験者向け採用ページから、ぜひお気軽にお問い合わせください。